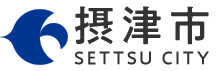児童手当
更新日:2024年11月12日
制度改正について
令和6年10月分からの児童手当について、次のとおり制度が改正されました。
【主な改正内容】
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象を高校生世代まで延長
(3)第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
(4)支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更
児童手当-令和6年10月からの制度改正に伴う申請手続きについて
受給資格のある方
- 18歳の年度末まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の日本国内に居住する児童(留学等は除く)を養育している本市に住民登録がある方
- 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母
父、母ともに所得がある場合は、生計の中心となっている方が受給対象者となります。 - 離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に支給します。
離婚協議中であることがわかる書類等の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。 - 児童を監護し、かつ、生計を同一にする未成年後見人
- 父母に養育されていない児童を監護し、かつ、生計を維持する方
- 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、かつ、生計を同一にし、かつ、当該父母が指定した方
- 児童福祉施設等の施設設置者など
| 「監護」 | 児童を監督・保護のもとに養育していることです。 |
|---|---|
| 「生計を同一」 | 請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を含みます。 |
| 「生計を維持」 | 請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。 |
| 「児童福祉施設等」 | 対象となる施設等は以下のとおりです。
|
支給額
| 年齢等 | 第一子・第二子 | 第三子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上 高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
児童手当の人数の数え方
受給者が監護・養育している0歳から22歳の年度末までのお子さまを児童手当の人数として数えます。
18歳から22歳の年度末までのお子さまについては、進学や就職の状況を問わず、お子さまの生活費を負担し、かつ日常の世話などしていれば児童手当の人数として数えます(支給はありません)
お子さまが独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であっても児童手当の人数として数えません。
支給日
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までの手当(2ヶ月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
なお、本市の支給日は、各月の15日です。
※支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月15日 | 12~1月分 |
| 4月15日 | 2~3月分 |
| 6月15日 | 4~5月分 |
| 8月15日 | 6~7月分 |
| 10月15日 | 8~9月分 |
| 12月15日 | 10~11月分 |
認定請求や現況届等で、提出が必要な書類等がある場合、それらを全てご提出いただいてからの支給となります。
市外への転出などにより、本市での受給事由が消滅した場合は、その届出の日又は消滅した日(いずれか遅い方)の翌月の15日に支給します。
支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。
請求手続きについて
請求手続き
出生や転入などで、摂津市で新たに児童手当を受給することができるようになった場合は、速やかに申請をしてください。申請が遅れますと、支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。(手当の増額手続きも同様です。)
- 手当の支給は、申請を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などの日から15日以内に申請をいただくと、その日の翌月分から支給されます。さかのぼって支給されませんので、ご注意ください。
- 公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は、勤務先での支給となります。(勤務先でご確認ください。)
公務員を退職した場合や、公務員の方が独立行政法人に勤務または外郭団体に派遣された場合も、退職日から15日以内にこども政策課に申請をしてください。
必要なもの
新たに児童手当を受給される時
- 児童手当 認定請求書
- 請求者名義の金融機関口座の分かるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
- 窓口でお手続きされる方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者及び配偶者分)
- 別居監護申立書(児童と別居している場合のみ)
その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
手当の増額の時(第2子以降の出生等)
- 児童手当 額改定請求書
- 別居監護申立書(児童と別居している場合のみ)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(別居児童分)
その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
児童手当額改定請求の電子申請について
国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル※1を使って、児童手当額改定請求を電子申請で提出することができるようになりました。
※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。
こんな時はお届けが必要です。
| 提出を必要とするとき | 届の種類 |
|---|---|
| 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
| 振込口座を変更するとき | 口座振込依頼書 |
| 銀行の統合などで口座番号が変わったとき | 口座振込依頼書 |
| 他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
| 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
| 養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
請求書
第1子出生の時、または摂津市に転入したとき等に必要な請求書(健康保険証の写し等、添付書類が必要な場合がありますので、上記「必要なもの」を参照)
児童手当 認定請求書記入例 (PDFファイル: 505.0KB)
記入箇所を例示しています。
児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル: 183.1KB)
第2子以降を出生した時等の増額、減額に必要な請求書(添付書類が必要な場合がありますので、上記「必要なもの」を参照)
児童手当 額改定認定請求書の記入例 (PDFファイル: 307.8KB)
記入箇所を例示しています。
児童と別居している場合に必要な添付書類
別居監護申立書の記入例 (PDFファイル: 104.2KB)
記入箇所を例示しています
戸籍上、児童が請求者の子となっていない場合に必要な添付書類
記入箇所を例示しています
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 こども政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1980
ファックス:06-6319-1930
メールでのお問い合わせはこちら