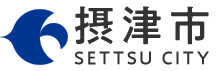明和池遺跡(QRコード用抜粋)
更新日:2019年09月26日
明和池遺跡 摂津市庄屋1丁目 顕彰札
この付近は明和池遺跡と呼ばれていました。昭和八年(一九三三年)、庄屋一丁目にあった明和池の底土から弥生と古墳時代の土器が発見され知られるようになりました。
昭和六十二年に本格的な発掘調査が行われて、七つの時期の地層が認められました。最も古い時代は弥生時代中期のもので、最も新しい時代は戦国時代のものでした。
- 弥生時代中期(土器)
- 弥生土器後期~古墳時代前期(自然河川、土器、青銅器鋳造関連遺物)
- 古墳時代後期(掘立柱建物跡・土坑・溝、土器)
- 平安時代(掘立柱建物跡、土器・石帯)
- 鎌倉時代(掘立柱穴・土坑・大溝・溝、土器・陶磁器)
- 室町時代(掘立柱穴・土坑、土器・陶磁器)
- 戦国時代(大溝・土坑、土器・陶磁器)
調査の結果、明和池遺跡では、少なくとも二千年前には人間が住んでいたと思われます。
平成二十二年に吹田操車場跡地の土地区画整備事業に先立つ発掘調査が行われ、弥生時代後期(今から1800~2000年前)の集落跡が発見されました。人々が生活していたことを示すものとして、竪穴建物と呼ばれる地面を掘り下げて床を作った建物が見つかりました。建物のすぐ脇には、当時の川の跡が見つかり、川べりから、生活に使用したと考えられるたくさんの弥生土器が発見されました。
平成二十三年の発掘調査では古墳時代後期(今から1400~1500年前)の川の跡が発見され、川の中からは、須恵器と呼ばれる青灰色の土器が多量に見つかりました。明和池遺跡の北側には、千里丘陵と呼ばれる広大な丘陵地があり、古墳時代の窯跡がたくさん見つかっています。明和池遺跡の川の中から発見された須恵器も、こうした窯場で作られたものと考えられます。
調査では、奈良時代~平安時代の川の跡も見つかっており、人面墨書土器と呼ばれる、土器の表面に顔を描いた土器や、土馬などの「まじない」の道具も発見されています。こうした祭祀遺物は、当時の都や役所関係の施設から、発見されることが多く、都との関係が非常に密接であったことが考えられます。
平成二十七年の発掘調査では、弥生時代後期(今から1800~2000年前)の竪穴建物などの住居址が発見されるとともに、青銅器の鋳造に使用していたと考えられる土器や金属類が出土しており、明和池遺跡に住んでいる人々が青銅器の鋳造を行っていたことが確認されました。

平成22年度発掘調査「弥生時代の集落跡」
QRコード用抜粋について
顕彰板の実物に貼付してあるQRコードを読み込むと、この抜粋ページを開くことができます。
内容は全件のページと同様ですので、
市内顕彰板の情報を一括でご覧になられたい場合は、以下のリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 教育総務部 生涯学習課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1766
ファックス:06-6319-5066
メールでのお問い合わせはこちら