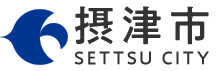【こどもの食コラム】家族で一緒に食べましょう!
更新日:2025年02月19日
毎月19日は

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。
家族で食べると体も心も育ちます
幼児期の食体験は大人になっても影響が続く食生活の基礎となります。食事は体の成長だけでなく、心の発達にも大きな役割を担っています。食事を通して得られる心の発達は、こどもと大人が一緒に食事をすることで得られます。家族で囲む食卓はこどもの居場所であり、親に守られていると安心する場所でもあります。
離乳後期頃から家族みんなで食べる機会を作り、食事のおいしさ、楽しさを共有していきましょう。大人が食べる様子を見せて、すぐに真似はできなくても見る機会を与えられるとOKです。2歳ぐらいになると大人の言うことを理解し始め、大人の真似をするようになり、一緒に「おいしいね」と共感することもできるようになります。この頃から食事前の手洗いや挨拶などのマナーを教えていきましょう。
家族で食べると良いことばかり!
1.食事が楽しみになる
家族が揃って楽しい雰囲気で食事をしていると、こどもが食事の時間を楽しみにし、食べたい意欲が育ちます。「上手に食べたね!」とほめることで、こどもの意欲をさらに伸ばしていきます。
2.栄養のバランスが整いやすくなり、偏食の固定化を避けられる
幼児期の偏食は固定されたものでなく、時期により嫌う食品が変化していきます。大人がおいしそうに食べるのを見ると、こどもも苦手なもの、初めて見るものにもチャレンジしてみようと意欲が湧きます。さらに家族に応援してもらったり、ほめてもらうと克服しようという気持ちが育ちます。
3.大人を見て、食事のマナーや姿勢が身につく
食事の挨拶やスプーン、お箸の使い方、他の人を思いやるなど、社会生活の基本となる食事のマナーについて、こどもは大人を見て自然に学んでいきます。このような食事のマナーは、家族揃って食事をするときに、楽しい雰囲気の中で教えていくのがポイントです。
4.コミュニケーション能力が養われる
みんなと一緒に食べながら話をしたり、聞いたりすることで、人との会話をしながら食事を楽しめるように発達していきます。「おいしいね」「もっと食べる?」などの会話が思いやりの気持ちを育み、社交性を養います。
5.一緒に味わって食べる感覚が発達する
一緒に食べる大人が「おいしいね」「つめたいね」など、こどもの口の中の感覚や味わいを共感して伝えることが、味覚の発達を助けます。こどもの好きなものばかりを与えていたり、親とは別のものを与えていると、食体験の幅が広がりにくく、味わって食べる感覚が発達しにくくなります。

食事の時間がなかなか合わないときは・・・
1歳頃になると、1日1回は家族で食べられるようにするのが望ましいですが、保護者の帰宅時間が遅くなってしまう場合など、こどもの夕食の時間は遅く設定しないよう注意します。夕食の代わりに朝食を一緒に食べる、1日1回が難しければ週末だけはゆっくり食事を一緒に食べるようにするなど工夫して、一緒に食べる機会が全くないことを避けましょう。
※関連コラム
摂津市公式クックパッドでは・・・
こども向けの様々なレシピをご紹介しています。
毎日の食事作りにぜひお役立てください!
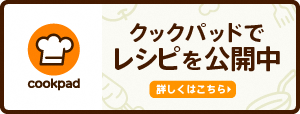
https://cookpad.com/kitchen/50330313
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 出産育児課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6170-2181
ファックス:06-6170-2182
メールでのお問い合わせはこちら