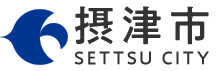保育所・認定こども園(保育部分)等随時入所について
更新日:2025年04月01日
随時入所について
| →保育施設一覧(R7.4.1版) | →保育施設マップ(R7.4.1版) |
必要書類について
申し込みに必要な書類は、世帯の状況により異なりますので、必ず「保育所等入所案内」のP10~P11をご確認のうえ、下のリンクから印刷して使用してください。(ここには所定の様式があるもののみ掲載しています。)
入所申込について
1. 保育所・認定こども園(保育部分)等を利用できる方
保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業等の認可保育施設における保育は、保護者の就労、病気その他の理由により保育の必要性の認定を受けた場合に利用することができます。そのため、「小学校入学準備のため」や「集団に慣れるため」、「友達を作るため」、「教育のため」などの理由だけでは、利用いただくことはできません。なお、市内の認可保育施設は、原則として、市内に居住し住民登録をしている児童に限り、利用することができます。
| 認定こども園(1号認定(教育)部分)や幼稚園の入園は、各園での受付です(当案内による申込手続きではありません。)。入園申込書類の受付期間や受入年齢等の募集状況は、各園により異なりますのでご注意ください。なお、これらの施設の利用にあたっては、保育の必要性の認定は不要です。 |
2. 保育を必要とする理由の認定
保育の利用にあたっては、次の2 号又は3 号の教育・保育給付認定を受ける必要があります。
- 1号認定…満3歳以上で教育を希望する子ども 利用先 幼稚園、認定こども園(教育部分)
- 2号認定…満3歳以上で保育が必要な子ども 利用先 保育所、認定こども園(保育部分)
- 3号認定…満3歳未満で保育が必要な子ども 利用先 保育所、認定こども園(保育部分)他(注釈)
(注釈)3号認定のその他の利用先には、小規模保育事業等の地域型保育事業が含まれます。
2 号又は3 号の認定を受けるためには、下記1.~10.のいずれかの事由に該当する必要があります。
また、保育標準時間認定と保育短時間認定の区分があり、次のとおり、それぞれの1 日の最大利用時間が異なります。
- 保育標準時間認定…1日最大11時間
- 保育短時間認定…1日最大8時間
- 延長保育により最大時間を超えた利用も可能です。
(延長保育の実施状況は保育施設により異なります。) - これらはあくまで最大の利用時間であり、実際の保育時間は、世帯ごとに必要とされる時間帯となります。具体的には、入所(園)時に各施設とご相談いただくこととなります。
保育の必要性が認定される事由
- 就労(1カ月に64時間以上)
64時間以上120時間未満は短時間認定、120時間以上は標準時間認定
120時間未満であっても、標準時間認定とすることが適当と認められる場合は標準時間認定 - 出産前後 標準時間認定
- 保護者の疾病、負傷、精神や身体に障害(相当)があること 標準時間認定
- 同居親族(長期入院中の親族を含む)の常時介護又は看護 標準時間認定
- 災害、風水害、火災などの復旧にあたっていること 標準時間認定
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること 短時間認定
- 就学(月64時間以上。職業訓練学校等における職業訓練を含む)就労に準じて標準時間または短時間認定
- 育児休業中であるがすでに施設を利用している子どもがいて継続利用が必要と判断される場合 短時間認定
- その他、上記の各事由に類すると市長が認める事由 類する事由に準じて標準時間または短時間認定
認定の有効期間
保育認定の事由ごとの有効期間は次のとおりです。認定事由がなくなると、原則として保育施設を継続して利用することはできません。
有効期間を経過後も、引き続き保育所等の利用を希望される場合は、改めて保育の必要な理由を証明する書類が必要です。
| 保育認定の事由 | 有効期間(保育所等の利用が可能な期間) |
|---|---|
| 就労(月64時間以上) | 小学校就学までの範囲内 |
| 出産前後 | 出産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後8週間の期間 |
| 保護者の疾病、負傷又は障害(相当) | 必要と認められる範囲内 |
| 同居親族(長期入院中の親族を含む)の常時介護又は看護 | 必要と認められる範囲内 |
| 災害、風水害、火災などの復旧にあたっていること | 必要と認められる範囲内 |
| 求職活動(起業のための準備期間を含む) | 入所から90日経過した月の末日 |
| 就学(月64時間以上。職業訓練学校等における職業訓練を含む) | 保護者の卒業までの範囲内 |
| 育児休業中であるが既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要と判断される場合 | 育休に係る子どもが満1歳に達する日の月末。ただしやむを得ず育休を延長した場合はその子どもが2歳に達する日の月末 |
| 上記以外の事由 | 必要と認められる範囲内 |
認定を受けるために必要な書類
入所申込み時の必要書類としては、「4.申込み時の必要書類」をあわせてご覧ください。
| 保育が必要な理由 | 必要書類 |
|---|---|
| 居宅外労働 | 就労証明書(就労内定の場合は、その証明書を受けてください。) |
| 内職 | 内職証明書(就労内定の場合は、その証明書を受けてください。) |
| 自営業 | 就労証明書及び自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、又は開業届等) |
| 出産前後 | 母子健康手帳の写し(父母の氏名と出産予定日が記載されているページ) |
| 傷病 | 保育が必要である旨の記載がある傷病証明書又は診断書 |
| 障害又は障害に相当する場合 |
1 障害による手帳等の交付を受けている方・・・身体障害者手帳等、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し 2 障害による手帳等の交付を受けていない方・・・診断書 |
| 同居親族の介護・看護 | 介護・看護申立書及び介護又は看護が必要なことがわかる書類(診断書、要介護の認定を受けているとわかる介護保険証の写し等) |
| 求職活動 | 誓約書兼求職活動報告書 |
| 就学 | 在学時間がわかるもの(時間割等)及び在学の証明書(在学証明、学生証の写し等) |
| 育児休業 | 育児休業証明書又は育児休業の取得期間が記載された就労証明書 |
- 上の表に当てはまらない場合の必要書類については、保育教育課へお問い合わせください。
- 入所後においても、入所要件を確認するため保育が必要な理由を証明する書類を提出していただくことがあります。
必要書類の提出が必要な方の範囲について
保育が必要な理由を証明する書類は保護者一人につき1枚必要です。
18歳以上65歳未満の同居家族がおられる場合は、利用調整(入所の選考)の資料として使用しますので保護者以外の同居者の証明書もご提出ください。提出がない場合は、保育可能な方と同居していると判断し、保育の必要性が低いとみなして減点となります。
3.入園申込みの受付
(1)令和7年4月入所選考の受付
一斉入所の受付は終了しました。
(2)令和7年5月~令和8年1月入所選考の受付
申込締切:入所希望月の前月10日(10日が土日祝にあたる場合は、翌平日)
申請先:市役所新館6階保育教育課
申請方法:書面申請(窓口、郵送(必着))
入所日:やむをえない場合を除き、毎月1日付け
(3)令和8年2月および令和8年3月入所選考の受付
申込締切:令和7年12月10日
※入所月の前月ではありませんのでご注意ください。
申請先:市役所新館6階保育教育課
申請方法:書面申請(窓口、郵送(必着))
入所日:やむをえない場合を除き、毎月1日付け
4. 申込み時の必要書類
入所申込み時には、次の1~6(6は必要な方のみ)の書類をそろえて提出してください。
- 保育所等入所申込書(兼保育児童台帳)…申込児童1名につき1枚(裏面あり)
- 子どものための教育・保育給付認定申請書…申込児童1名につき1枚
- こどもの健康・育ち調査票…申込児童1名につき1枚
- 保育所等入所申込に関する確認・同意書…1世帯につき1枚
- 保育が必要な理由を証明する書類…以下のいずれかの書類を、父母それぞれ1枚ずつ
[就労証明書、内職証明書、誓約書兼求職活動報告書、傷病証明書、介護・看護申立書、母子手帳の写し、在学時間がわかるもの及び在学の証明書等] - その他の書類…次の項目に該当する方のみ必要
(6-1)小学校未満の兄姉が、私立幼稚園等の保育園以外の施設に通っている場合…在園(通園)証明書
(6-2)生活保護受給世帯…生活保護受給証明書
(6-3)障害がある方と同居している世帯…次の手帳等の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金等の年金証書、特別児童扶養手当の受給者証)
(6-4)入園児童に別居の兄姉がいる世帯…別居世帯員申立書
(6-5)認可外保育施設等を利用している場合…認可外保育施設等利用証明書(※月間64時間以上、16日以上の利用実績が必要です。)
5.申込みに関する相談
入所申込に関する事前相談を随時受け付けています。
相談日時:平日午前9時~12時、午後1時~5時
6. 入所の選考について
申込みされた内容(家族構成、保護者の状況、家庭環境その他の状況)により選考を行います。
5 月以降の入所申込については毎月16 日(16 日が土日祝日の場合は翌平日)(※令和8年2月及び3月入所選考については令和7年12月16日)に選考行います。保育の必要性が高い児童から順に入所の承諾をし、入所の案内ができる方には、電話でご連絡します。
待機となった場合、最初の選考の月末のみ保留通知書をお送りします。
なお、4 月入所の一斉受付の選考結果は、入所・待機にかかわらず、郵送で通知します。
施設の空き状況等により入所できないことがありますので、あらかじめご承知ください。希望月に入所できなかった場合は申込年度内に限り、次月以降も選考の対象となります。
7. 保育料
保育料は児童の年齢区分、時間認定区分、児童の同一世帯に属して生計を一にしている父母もしくはそれ以外の扶養義務者〔※家計の主宰者である場合に限る〕の市町村民税額等によって決定します。
保育料は毎月期限までに納入してください。
※それ以外の扶養義務者における「家計の主宰者」とは、保育施設入所児童を市町村民税の算定上扶養控除の対象としている者や、祖父母等と同居しており父母合わせての年収が103 万円未満の場合における祖父母等の親族のことです。
○具体的な金額や算定方法については、「保育所等入所案内」のP15~P16をご覧ください。
○3 歳以上児については、保育料は無償ですが、別途給食費(主食費・副食費)が必要です。
※副食費については免除される場合がございますので、「保育所等入所案内」のP17をご参考ください。
○延長保育を利用される方は、別途、延長保育料が必要です。
〇なお、給食費、延長保育料は保育施設により料金が異なります。
年収約360万円未満相当世帯の保育料多子計算における兄姉の範囲とQ&A (PDFファイル: 111.6KB)
保育料の変更
1.次のいずれかに該当する場合は、保育料が変更となる場合がありますので、保育教育課へご連絡ください。
(ア)~ (ウ)は該当することとなった日の翌月分以降の保育料、(エ)は欠席した月分の保育料がその対象となります。なお、事後のご連絡である場合は、年度内に限り、遡って変更可能です。
(ア) 所得の修正申告等により保育料決定の根拠となる年の市町村民税額に変更があるとき
(税務署や市民税課で手続きされた場合でも、保育教育課に変更内容のご連絡がなければ、保育料を変更できないことがあります。)
(イ) 婚姻・離婚・死別その他の事情により、世帯状況に変更があったとき
(ウ) 地震等の被災により、被害規模が半壊以上の罹災証明書が発行されたとき
(エ) やむを得ず長期欠席した場合で、次のAとBいずれにも該当する場合
A.児童の事故又は疾病等によること(診断書等の証明書類が必要です。)
B.15日以上連続して欠席すること
2.失業・傷病等によって所得が著しく減少し、保育料の支払いが困難となったときは、申請により、申請月の翌月分から保育料が変更となる場合がありますので、保育教育課へご連絡ください。
3.月途中の入退園があったときは、日割り計算により減額となる場合があります。
保育所等における給食費について
令和元年10月に開始された、幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児以上のお子さまの保育料に含まれていた副食費(おかず代)については、各保育施設における実費徴収へ変わりました。
8.入所承諾児童の健康診断
入所承諾児童については事前に健康診断を受けていただきます。その結果、医師が児童の健康上入所を不適当と判断したとき、児童に伝染性疾患があるときなどは入所をお断りすることがあります。
9.退園および保育の実施の解除
市外への転出や、保護者の退職などにより退園されるとき、および児童の病気などで長期欠席されるときは、必ず事前に保育施設および保育教育課へご連絡ください。
入園承諾後、入所中においても次のいずれかが判明したときは保育の実施を解除することがあります。
- 支給認定申請書、入所申込書類および面接調査のとき、虚偽の記入または申立があった場合
- 現に摂津市内に居住していない場合
- 世帯構成・退職など家庭状況の変更によって、保育の必要性の事由に該当しなくなった場合
退園届
退園の際に、保育教育課へ提出する届出書です。印刷してお使いください。
10.産休・育休明け入所予約
下記ページをご覧ください。
11.一時預かり
下記の「一時預かり事業のお知らせ」をご覧ください。
12.特別保育の実施
「休日保育利用のお知らせ」は下記をご覧ください。
「病後児保育利用のお知らせ」は下記をご覧ください。
「病児・病後児保育事業(エキスポキッズ)について」は下記をご覧ください。
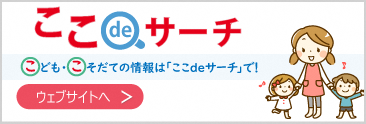
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 保育教育課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1184
ファックス:06-6319-1930
メールでのお問い合わせはこちら