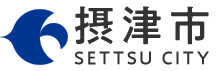高額療養費
更新日:2025年12月02日
高額療養費の支給申請について
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が申請により、高額療養費として支給されます。対象の世帯には支給申請に係る通知が送付されます。通知がお手元に届いた後に、申請が必要となります(※1)。
条件を満たす世帯に対しては、高額療養費の自動振込を行っています。希望される場合は国保年金課までお申し出ください(※2)。
※1 高額療養費は診療報酬明細書(レセプト)審査を行い、被保険者が診察を受けてから4~6か月で通知されますが、審査の内容によっては7か月以上かかることもあります。
※2 自動振込の同意書を提出されると、提出された翌月以降に高額療養費の支給がある場合、指定された口座へ自動的に振込が行われます。ただし、条件から外れた場合は自動振込は行われず、従来通り支給申請に係る通知が送付されますので、申請が必要となります。
高額療養費の自己負担限度額について
所得区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は、前年の所得により行います。
70歳未満の人の場合
70歳未満の人については、同じ月内に同じ医療機関で限度額を超えて自己負担した分が高額療養費の対象となります。また、異なる医療機関でも21,000円以上の自己負担額を支払った場合は高額療養費の合算の対象となります。
なお、同じ医療機関でも医科と歯科は別計算になり、また、外来と入院も別計算になります。ただし、薬局に支払った自己負担額は、処方した医療機関分と合算されます。
| 所得(※)区分 | 3回目まで |
4回目以降 |
|
|---|---|---|---|
|
所得901万円超 |
ア |
252,600円 +(総医療費-842,000円) ×1% |
140,100円 |
|
所得600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円 +(総医療費-558,000円) ×1% |
93,000円 |
|
所得210万円超 600万円以下 |
ウ |
80,100円 +(総医療費-267,000円) ×1% |
44,400円 |
|
所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※ 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が下がります。
ほかの市町村へ転出しても、同じ都道府県内であり住民票の世帯構成が同じ等の条件を満たしている場合、高額療養費の支給回数が引き継がれます。
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人については、同じ月内に限度額を超えて自己負担した分が高額療養費の対象となり、異なる医療機関で自己負担した分もすべて合算の対象となります。
|
所得区分 (下記「70歳以上75歳未満の 人の所得区分」参照) |
外来 (個人単位)[A] |
外来+入院 (世帯単位)[B] |
||
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
3 (課税所得 690万円以上) |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降 140,100円(※1)】 |
||
|
2 (課税所得 380万円以上) |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降 93,000円(※1)】 |
|||
|
1 (課税所得 145万円以上) |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降 44,400円(※1)】 |
|||
|
一般 (課税所得 145万円未満等) |
18,000円(※2) |
57,600円 |
||
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | ||
※1 過去12か月間で、高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)[A]の限度額を超えた支給回数は含みません。
※2 1年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。
70歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下表1.2.3.いずれかの場合は、申請により一般の区分と同様になります。対象の世帯には申請書が市役所から送付されます。
|
同じ世帯の70歳以上 75歳未満の国保被保険者数 |
収入 | |
|---|---|---|
| 1 | 1人 | 383万円未満 |
| 2 |
同じ世帯の国保を抜けて後期高齢者医療制度へ |
|
| 3 | 2人以上 | 合計520万円未満 |
一般
・同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の人。
・住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基準総所得額(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)」の合計額が210万円以下の人。
低所得者2
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)。
低所得者1
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたときや、控除したときに0円になる人。ただし、年金の所得は控除額を80万円(令和7年8月受診分以降は80.67万円)として計算。
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)制度について
「基準日」において、所得区分が一般、低所得者1・2の人で、「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が「年間上限額」を超える場合に、その超えた分が申請により支給されます(「計算期間」において月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額は差し引かれ計算されます)。
対象の世帯には支給申請に係る通知等が送付されます。振込は申請受付から約1~2か月後となります。
・基準日:毎年7月31日
・計算期間:前年の8月1日から7月31日までの1年間
・年間上限額:144,000円
申請に必要なもの
・国民健康保険高額療養費(外来年間合算)の支給申請についての通知
・国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・顔写真付きの公的身分証明書
・世帯主の口座がわかるもの
※ 年度途中で転職・転居等により医療保険者が変更となった場合、変更前の保険者における自己負担額も外来年間合算の対象となります。変更前の医療保険者から「自己負担額証明書」を受け取り、申請時に添付してください。
高額医療・高額介護合算制度について
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えた額が501円以上の場合、申請により支給されます。
申請後、決定通知が3~4か月後に送付され、支給決定の場合のみ振込されます(再計算のうえ支給決定されますので、支給額が変更になる場合や不支給になる場合がございます)。
| 70歳未満の人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所得区分 | 限度額 | |||
| 所得901万円超 | ア | 212万円 | ||
| 所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 | ||
| 所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 | ||
| 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | エ | 60万円 | ||
| 住民税非課税世帯 | オ | 34万円 | ||
| 70歳以上75歳未満の人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所得区分 | 限度額 | |||
| 現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) | 212万円 | ||
| 2(課税所得380万円以上) | 141万円 | |||
| 1(課税所得145万円以上) | 67万円 | |||
| 一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | |||
| 低所得者2 | 31万円 | |||
| 低所得者1 | 19万円 | |||
申請に必要なもの
・高額介護合算療養費支給申請についての案内書
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・顔写真付きの公的身分証明書
・世帯主の口座がわかるもの
限度額適用認定証について
医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)を医療機関の窓口で提示すれば、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払う自己負担額が上記の限度額までとなります(所得区分現役並み所得者3、一般の方については、「高齢受給者証」を医療機関の窓口で提示すれば、自己負担額が上記の限度額までとなります)。
認定証は国保年金課への申請により交付されます。申請書については下段の限度額適用認定証交付申請書欄から印刷できます。
また、マイナ保険証を利用する場合でも自己負担額が上記の限度額までとなり、認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください(対応している医療機関のみ)。
※ 所得区分オ、低所得者1・2の方については食事代や居住費の自己負担となる標準負担額が減額されます。標準負担額の減額については下記ページをご確認ください。
申請に必要なもの
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・顔写真付きの公的身分証明書
・入院日数が90日を超えることがわかる領収書等(所得区分オ、低所得者2の人で該当される場合のみ)
限度額適用認定証交付申請書
限度額適用認定証交付申請書 (PDFファイル: 101.7KB)
限度額適用認定証交付申請書(記入例) (PDFファイル: 160.2KB)
特定疾病療養受療証について
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(以下、受療証)を医療機関などの窓口に提示すれば、特定疾病に係る自己負担額は1か月1万円(人工透析が必要な慢性腎不全であり、所得区分ア、イの人は1か月2万円)までになります。
受療証は国保年金課へ申請し、特定疾病の認定を受け交付されます。申請書・意見書(ひな型)については下段の特定疾病療養受療証に関する様式欄から印刷できます。
また、認定後は対応している医療機関の窓口でマイナ保険証を提示することでも特定疾病に係る自己負担額の確認ができます。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
・意見書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・顔写真付きの公的身分証明書
特定疾病療養受療証に関する様式
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 国保年金課 国保医療係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1555
ファックス:06-6318-1350
メールでのお問い合わせはこちら