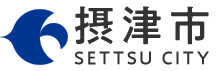睡眠と健康
更新日:2025年07月24日
ちゃんと眠れていますか? ~よい眠りとは~
睡眠は最も重要な休養行動です。しかしながら忙しくなると、まず削られるのが睡眠です。
良い睡眠のために、可能な限り6時間以上の睡眠時間の確保と、睡眠休養感を高めるよう生活にメリハリをつけ、睡眠の質を高める工夫をしましょう。
何時間眠ればいいの?

睡眠時間には年齢差・個人差があります。
仕事、家庭、趣味と忙しい生活を送っていると、慢性的な睡眠不足になりがちです。
毎日睡眠時間を十分に確保できるよう、生活を工夫しましょう。
睡眠と生活習慣病の密な関係
睡眠不足や、質の悪い睡眠を続けると生活習慣病になるリスクを高め、症状を悪化させることが分かっています。
睡眠と生活習慣病の関係
睡眠不足や質の悪い睡眠が続くと…
| 肥満 | 食欲を促進するグレリンというホルモンが上昇するため、食欲が増してつい食べてしまいます。さらに満腹ホルモンといわれるレプチンの分泌は低下し食べても満腹感がなかなか得られず、食べ過ぎてしまうという連鎖が起こります。 |
| 糖尿病 | 血糖コントロールを管理するインスリンの働きが悪くなり、血糖値が下がりにくくなるため糖尿病が悪化するおそれがあります。 |
| 血圧 | 血圧を上昇させる働きをする交感神経と血圧を下げる働きをする副交感神経の切替えがうまくいかず、血圧の調整ができなくなり高血圧になりやすくなったり、悪化させる原因となります。 |
摂津市民の睡眠について

令和5年度に実施した「まちごと元気!健康せっつ21(第三次)」アンケート結果では、睡眠による休養を十分取れていないと答えた市民が男女ともに3割を超えており、前回調査時の平成30年度よりも悪化しています。
休養が取れたと感じる睡眠のためにも、まずは睡眠時間をしっかり確保することから始めてみましょう。
健康づくりのための睡眠ガイド2023
厚生労働省は、「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を発表しました。
良い睡眠は、量(時間)と質(休養感)が重要です。
睡眠時間は長すぎても短すぎても健康を害する原因となり、朝目覚めたときに感じる休まった感覚(睡眠休養感)は良い睡眠の目安となります。
次の5原則は、睡眠時間を確保し、睡眠休養感を高めるポイントです。
日常生活で、できることからはじめましょう!
第1原則 適度な長さで休養感のある睡眠を
週末の寝だめ習慣は、平日の睡眠不足のサイン!体内時計が乱れないよう、平日に十分な睡眠時間を確保し、平日も休日も同じくらいの十分な睡眠時間を確保できるように心がけましょう。
第2原則 光・温度・音に配慮した、良い睡眠のための環境づくりを心がけて
寝る前・寝床の中でのデジタル機器の使用は、夜更かし・朝寝坊、睡眠不足を助長します。また、睡眠中は音が悪影響を及ぼすため、できるだけ静かな環境で眠ることが推奨されます。照明は、照度を落とし、季節に合わせて心地よい温度で快適に過ごせるようエアコンで室温の調整を。
第3原則 適度な運動、しっかり朝食、寝る前のリラックスで眠りと目覚めのメリハリを
ストレスが高い状態のまま寝床に入ると睡眠休養感が低下します。また、就寝直前の夕食や夜食習慣は眠りの妨げとなります。
しっかり朝食を摂ることで体内リズムと生活リズムを調整し、日中のうちにからだを動かしストレスを発散させ、寝る前にリラックスする方法を身につけましょう。
第4原則 嗜好品とのつきあい方に気をつけて カフェイン、お酒、たばこは控えめに
夕方以降のカフェイン摂取は、夜間の睡眠に影響します。また、晩酌での深酒や、眠るためにお酒を飲むこと(寝酒)は、睡眠の質を悪化させる可能性があります。
ニコチンには覚醒作用があることや依存性があることから、良い睡眠のためには喫煙しないことが推奨されます。
第5原則 眠れない、眠りに不安を覚えたら専門家に相談を
睡眠環境や生活習慣、嗜好品(カフェイン・アルコール・喫煙)のとり方を改善しても睡眠休養感が高まらない場合、不眠症、閉塞性睡眠時無呼吸などの睡眠障害や、うつ病が隠れている場合がありますので、医療機関に相談しましょう。
こころの健康と睡眠

寝付けない、熟睡感がない、早朝に目が覚めてしまう、疲れていても眠れない等の不眠症状は、こころの病の症状として現れることがあります。
実際、うつ病の多くの人に何らかの眠りの問題があります。逆に不眠のある人はうつ病にかかりやすいことも知られています。
このように、睡眠不足は、心身の不調を引き起こすだけでなく、メンタルヘルスの問題にもつながる可能性があります。規則正しい生活習慣を心がけ、快適な睡眠環境を整え、ストレスを溜め込まず、こころとからだの健康を維持しましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1386
ファックス:06-6383-5252
メールでのお問い合わせはこちら