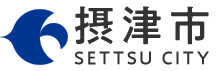住宅用火災警報器の設置及び維持管理について《動画あり》
更新日:2019年04月01日
摂津市火災予防条例が改正!!すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました!!
住宅用火災警報器CM
消防法及び火災予防条例改正の経緯
平成15年に住宅火災で亡くなられた人のうち、約7割もの人が「逃げ遅れ」が原因で命を落とされました。また、「逃げ遅れ」が多い理由としては、火災が発生した時間帯が夜間就寝中である例が多いことも原因であります。
しかし、住宅火災で亡くなられた何割かの人たちが、もし住宅用火災警報器を設置されており、火災発生を早期に知ることが出来ていれば助かった可能性があったと思われます。
このようなことから、平成16年6月に消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられることになりました。これを受け、本市におきましても火災予防条例を改正し、住宅用火災警報器の設置に関する規定を盛り込み平成18年6月1日から施行されることとなりました。
アメリカなどでは、すでに住宅用火災警報器の設置が義務付けられており、17年間の普及推進により住宅火災における死者数が約40%減少するという効果が出ています。(下記グラフ参照)
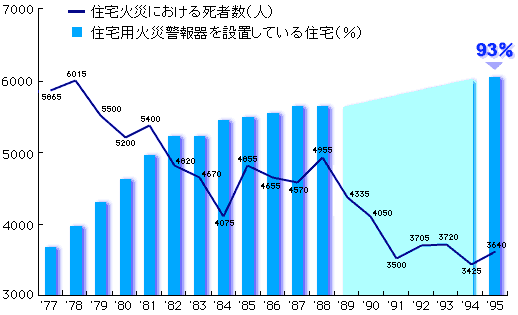
【アメリカ合衆国における住宅火災での死者数及び住宅用火災警報器の普及率】
いつから設置が義務化されたの??
平成18年6月1日以降の新築住宅は設置されていますが、既存住宅は、猶予期間の終了に伴い平成23年6月1日から義務化されています。
設置されていない方は、早急に設置してください!!

どこに付けるの??
住宅用火災警報器を住宅のどこに設置しなければならないかといいますと・・・下の図(設置例)をご覧いただきたいのですが、設置が義務付けられるのは、まず「寝室」です。次に、寝室がある階の「階段」ということになります。
住宅の寝室や階段等の配置によリ多少異なる場合がありますので、詳しくは消防本部予防課へお問合せくだい。
また、設置の義務はありませんが、「台所」などの火を使用する場所にも防火安全上、設置することをお勧めします。(市町村によリ、「台所」に警報器の設置を義務付けている場合もありますのでご注意ください。)
住宅用火災警報器は、「寝室」や「階段」などには煙を感知して警報を発する「煙式警報器」を義務付けております。また、煙や蒸気が発生しやすい「台所」などに設置する場合は、熱を感知して警報を発する「熱式警報器」の設置をお勧めします。
自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている共同住宅やマンションの寝室は、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。ただし、設置されていない場合は、住宅用火災警報器の設置を義務付けています。
住宅内における警報器設置例

設置が義務付けられている場所

設置を推奨する場所

2階の場合
3階以上の場合の設置例

3階以上の場合
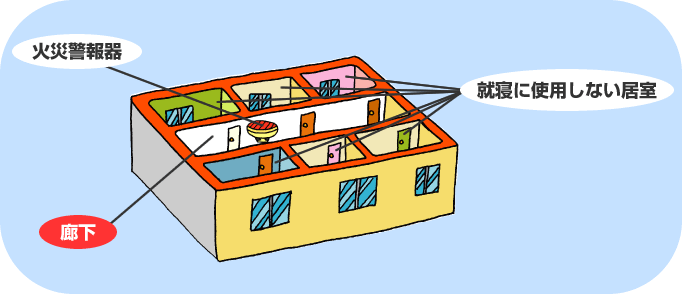
寝室に使用しない部屋(7平方メートル以上)が5以上ある階には廊下にも設置が必要。
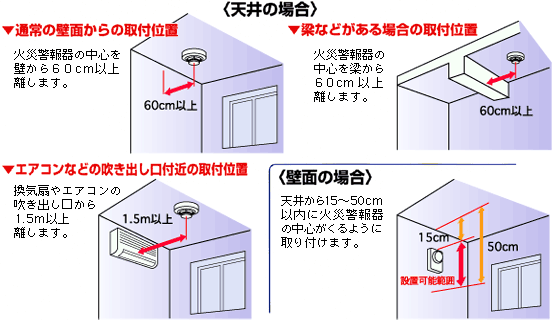
設置場所の詳細
どこで購入したらいいの??
消防設備業者、ホームセンター、大手家電販売店などで購入できます。
その他の住宅用火災警報器に関する相談は次の窓口でも受けておりますので参考にしてください。
- 財団法人 大阪府消防設備協会…06-6943-7654
- 住宅防火対策推進協議会…ホームページへリンク。
- 住宅用火災警報器相談室…0120-565-911
(財団法人日本消防設備安全センターが開設した相談窓口で、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までが受付時間となっていますのでご注意ください。)
検定を受けていない住宅用防災警報器とは??
平成25年3月27日に消防法施行令の一部が改正され、住宅用防災警報器が検定対象機械器具等の品目に追加されました。
検定対象機械器具等に追加された品目は、販売し、又は販売の目的で陳列し、また、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用すること(以下「販売等」という。)を行うためには、検定を受けて合格し、表示を付すことが必要となります。
それ以降、検定対象機械器具等として表示を付したものの販売等が開始されているところですが、経過措置として平成31年3月31日までは、表示が付されていなくても販売等を行ってもよいとされていました。
平成31年4月1日からは、経過措置期間が終了し、検定を受けて合格し、表示が付されたもののみしか販売等ができなくなります。
すでに設置されているものは、機能に異常等がない限りは交換する必要はありませんが、製造後10年を目安に交換を推奨していますので、交換する場合は、検定合格品である必要がありますのでご注意ください。

・NSマーク・
平成31年3月31日まで販売等が認められている。
・検定マーク・
平成31年4月1日から検定マークの付されたものしか販売等ができない。
悪質業者に注意!!
住宅用火災警報器が、法律により設置が義務化されることに伴い、訪問販売などで市場価格より高額で販売する悪質な業者が現われることが懸念されています。
住宅用火災警報器は、市場価格では 1個3,000円程度のものから10,000円程度のものが一般的です。
しかも、業者に依頼しなくても誰でも取り付けていただけます。
維持管理について!!
住宅用火災警報器は、万が一の際に備えて適切な維持管理が必要です!!
作動確認について
確認方法は、ボタンを押したり、ひもを引いたりするなど、機種によって異なります。定期的に作動確認をしましょう。
汚れていたら
ホコリが付くと火災を感知しにくくなることや、誤作動することがあります。中性洗剤を浸して固く絞った布で軽く拭きましょう。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
電池交換を忘れずに
乾電池タイプは電池の交換を忘れないように気を付けましょう。電池が切れそうになったときは、音や光で交換時期を知らせてくれます。
本体の交換について
自動試験機能付の住宅用火災警報器は、表示された交換期限又は、機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。
自動試験機能の付いていない住宅用火災警報器は、本体に表示されています。取付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換時期がきたら本体ごと交換してください。
作動確認をしても、警報が鳴らない時は?
電池の寿命又は電池ホルダ部のサビなどが考えられます。電池を新しいものに交換又は電池接続部分を確認してください。
電池を新しいものに交換しても作動しない場合は、住宅用火災警報器の故障も考えられますので、販売店又はメーカーにご相談ください。
火災でないのに警報がなってしまう時は?
タバコの煙、調理時の湯気や煙、ほこりなどが原因で住宅用火災警報器が鳴る場合は、数分間で警報が停止しますが、この現象が頻繁に発生する時は取付け位置を変更しましょう。
「ピッ」と短い音が一定の間隔で鳴る場合は、電池切れの注意音です。電池を新しいものに交換してください。電池を交換しても注意音が鳴り続ける場合は機能異常が考えられますので、新しい住宅用火災警報器とお取替えください。
燻煙(くんえん)式の殺虫剤を使用する時は?
燻煙式の殺虫剤等を使用する場合は、住宅用火災警報器が警報を発することがありますので、取外す、ビニール等で覆うなどしてください。(燻煙式の殺虫剤等を使用した後は、速やかに元に戻してください。)
画像をクリックして動画を見よう!(動画発信元:日本消防検定協会)
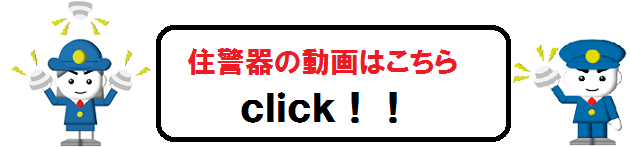
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・消防署
〒566-8555摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
電話:(代表)06-6381-0119 (消防総務直通)06-6381-1171 (予防直通)06-6318-1199 (警備企画直通) 06-6382-0119
ファックス:(代表)06-6319-5771 (消防総務・予防・警備企画)06-6319-5791
メールでのお問い合わせはこちら