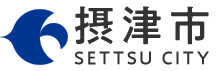防災教育の取組み(摂津小学校)
更新日:2019年02月28日
授業参観日に摂津小学校3年生で防災の授業が実施されました。
2月21日(木曜日)5時間目、自然災害が発生し、電気、ガス、水道が使えなくなったことを想定して、「もしもの時のこと」を考える防災の授業が実施されました。
初めに、大規模な自然災害が発生したとき「できなくなること」について考え、児童からは、「電話が使えない」「お風呂に入れない」「料理ができない」「夜電気をつけられない」等たくさんの意見が出されました。
担任が、困ったことがたくさんあっても、今あるものを工夫して困ったことを解消できないかを「考えること」が大切であることを伝えました。その工夫の一つとして、「代用品を作る」ことが考えられると児童に提案しました。
その後、「食器が割れて使えなくなったら」という想定で、身近にある新聞紙で食器(コップ)を作成しました。児童が作った新聞紙のコップに、ポリエチレン製の袋をかぶせ、実際に水を入れ、使用できることを確認しました。
授業の振り返りでは、「災害が起きると、困ったことがたくさんあることが分かった。準備をするために、災害についてもっと知りたいと思った」等の意見が出ました。
授業者は、今日学習したように、大規模な自然災害が起きてしまったときにどうすればよいかを考えることはとても大切であるが、災害が起こった後にできることは少ない。今日、家に帰って、お家の人と自然災害が起こったらどうするのかについて話をすること、災害が起こる前にいろいろなこと想定し、対策を考えておくことが大切であることを児童と参観に来られた保護者に伝えました。