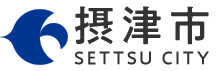【こどもの食コラム】食べ物による窒息事故にご注意ください
更新日:2022年12月19日
毎月19日は

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。
食べ物が詰まってしまう原因

乳幼児期に食べ物がのどに詰まってしまう主な原因として、お口の中の成長に合っていない形態の食べ物を食べて、そのまま丸のみしてしまうことにあります。月齢や年齢だけでなく、舌の動きや生えている歯の本数を見てどのような形態の食べ物を食べられるか検討することが必要です。また、普段食べている食材でも「遊びながら、歩きながら、寝転びながら」食べることで窒息につながる可能性があることも認識しておきましょう。
窒息事故につながりやすい食べ物
どんな食べ物でも窒息してしまう可能性はあるのですが、食品表面の滑らかさ、弾力性、固さ、噛み切りにくさといった食感や、大きさ、形状などが窒息事故につながると推測されます。特に気をつけてもらいたい食べ物の形状は下記のとおりです。
1.弾力があるもの → こんにゃく、きのこ、練り製品(かまぼこなど) 、ソーセージなど
2.なめらかなもの → 熟れた柿やメロン、豆類 など
3.球形のもの → プチトマト、乾いた豆類 など
4.粘着性が高いもの → 餅、白玉団子、ごはん など
5.固いもの → かたまり肉、えび、いか など
6.唾液を吸うもの → パン、ゆで卵、さつま芋 など
7.口の中でばらばらに なりやすいもの → ブロッコリー、ひき肉 など

また、飲食物が食道ではなく気管に入ってしまう、誤嚥の危険性もあります。乳幼児の気管の直径は1cm未満ととても狭いです。特に硬い豆、ナッツ類などの小さくて軽いものは、食べながら息を吸い込んだ時など、間違えて食道ではなく気管や肺に入ってしまうことがあるので、すりつぶしや粉末でない状態では5歳まで与えないように注意しましょう。
【消費者庁】食品による子どもの窒息・誤嚥(ごえん)事故に注意!―気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は5歳以下の子どもには食べさせないで―
実際に窒息死事故の原因となった食べ物
消費者庁の報告によると、窒息事故の原因となった食品は飴、菓子類(飴を除く)、果実類、豆・ナッツ類などとなっています。
平成22年から平成26年までの5年間で、子供(14歳以下)の食品が原因の窒息死事故103件の原因となった食品と発生件数は下図のとおりです。また、103件のうち87件が6歳以下の子供で発生していることが確認されました。養育者が食べ物の形状だけでなく、食べ方にも注意して見守りましょう。

食品による子供の窒息事故を予防するポイント
お子さんの誤飲誤嚥のリスクを理解しながら、適切な形状、食べ方になるよう家族でサポートしていきましょう。
(1)食品の与え方
1.食品を小さく切り、食べやすい大きさにして与えましょう。
2.一口の量は子供の口に合った無理なく食べられる量にし、飴やタブレットなど喉に詰まりやすい食品を食べさせる場合は大きさに注意しましょう。
3.誤って気管に入りやすいピーナッツなどの硬い豆・ナッツ類は、3歳頃までは食べさせないようにしましょう。
4.乳幼児にとって危険な食品を与えないよう、家族で環境に注意し守りましょう。
(2)食事中に注意すること
1.遊びながら、歩きながら、寝転んだまま食品を食べさせないようにしましょう。
2.急いで飲み込まず、よく噛み砕いてからゆっくりと飲み込むよう促しましょう。
3.食事の際は、お茶や水などを飲んで喉を湿らせましょう。
4.食品を口に入れたまま話したり、何かをしながら食事をしたりさせないようにしましょう。
5.食事中に眠くなっていないか、正しく座っているかに注意しましょう。また、 食事中に驚かせないようにしましょう。
※参照
○消費者庁からの注意喚起
「食品による子供の窒息事故に御注意ください!」(平成29年3月15日)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/170315kouhyou_1.pdf
○教育・保育施設等における事故防止及び 事故発生時の対応のためのガイドラインhttps://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/office/pdf/s59-4.pdf
摂津市公式クックパッドでは…
お子様向けの様々なレシピをご紹介しています。
毎日のお食事作りにぜひお役立てください!
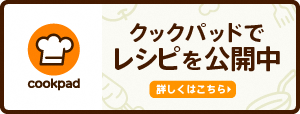
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 出産育児課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6170-2181
ファックス:06-6170-2182
メールでのお問い合わせはこちら