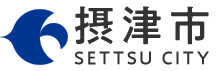【食育コラム】災害時に備蓄しておきたい食品
更新日:2025年03月19日
毎月19日は

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。
災害への備えを
地震・台風等の災害が発生し、被災してしまうと日常生活を送ることが困難になります。自分たちの健康と暮らしを守るために日常的な行動を見直し、いつ起こるかわからない災害に備えましょう。
今回は、医薬基盤・健康・栄養研究所 災害栄養情報研究室の先生方に災害時に気をつけたい栄養・食生活について伺いました。
災害時に起こる食と栄養の問題
地震や台風等の災害から身を守ることができても、長引く避難生活でストレスがかかることはもちろん、食生活の変化が心身の健康状態に影響を及ぼすことで健康を損ない、いわゆる災害関連死につながる可能性があります。
なぜ食品の家庭備蓄が必要なのか
東日本大震災や熊本地震では、災害発生から水道、電気、ガス等のライフライン復旧まで時間がかかりました。大規模な災害では、災害支援物資が5日以上到着しないことや、物流機能の障害によってスーパーマーケットやコンビニなどで食品が手に入らないことが想定されます。
このため、最低3日~1週間分×人数分の食品の家庭備蓄が望ましいといわれています。
ローリングストック
普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限が古いものから使い、使った分を買い足すことをローリングストックといいます。
ローリングストックは常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法で、費用や時間の面で、普段の買い物の範囲でできること、買い置きのスペースを少し増やすだけで済むというメリットがあります。
主に災害時に使用する「災害食」だけでなく、日常で使用し、災害時に使えるものを「ローリングストック」としてバランスよく備えることが大事です。
研究から見える家庭備蓄をしておきたい食材
大規模な自然災害によって避難生活が長引くと、肥満に該当する人が増えることがわかりました。肥満は様々な健康問題をひき起こす可能性があり、被災後も食事に気を付ける必要があります。どのような食生活が被災後の肥満を予防できるかについて、東日本大震災の被災者を追跡した大規模コホートの参加者を対象として、研究が行われました。
この研究では、魚介類摂取頻度と被災約2年後の肥満新規該当者の関連について分析が行われ、魚介類を食べる頻度が高いほど肥満に該当した人が少ないということがわかりました。この関連は、男性でのみみられ、特に仮設住宅で暮らす人に強くみられました。日頃から魚介類を食べる習慣をつけ、魚の缶詰などを備蓄しましょう。
引用:災害後の肥満をシーフードで予防 東日本大震災における魚介類摂取と被災後の肥満新規発症との関連:RIAS研究(国立健康・栄養研究所 災害栄養情報研究室)
摂津市公式キッチンでは…
災害時にも魚が食べられるよう、レシピを公開しています。ぜひ、作ってみてください!


この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1386
ファックス:06-6383-5252
メールでのお問い合わせはこちら