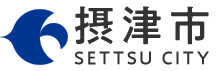【食育コラム】糖尿病の食事のポイント
更新日:2023年11月19日
毎月19日は

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。
11月は糖尿病予防月間
11月14日は世界糖尿病デーです。
世界糖尿病デーのある11月は糖尿病予防月間です。
今年も全国各地で糖尿病撲滅のためのシンボルカラーである青のライトアップが糖尿病予防月間に合わせて実施されます。
糖尿病とは
透析導入の原因、第一位は糖尿病性腎症ということを知っていますか?
糖尿病とは、インスリンが十分に働かないために血中を流れるブドウ糖という糖(血糖)が増えてしまう病気です。
血液中のブドウ糖濃度(血糖値)を下げる働きをするホルモンはインスリンだけです。糖尿病の予防には食後の急激な血液中のブドウ糖濃度(血糖値)の上昇を抑え、インスリンの分泌を節約することが大切です。
糖尿病に関する詳しい内容は下記をご参照ください。
食事から予防しよう!
調理のポイント
「おいしく」、「楽しく」続けることが大切です。食品選びだけでなく、いつもの調理法や味付けを見直してみましょう。少し工夫するだけで、満腹感を得ることができたり、血糖値を上げにくくすることができます。
食物繊維を取り入れましょう
食物繊維には食後の血糖値の上昇を抑えてくれる作用などがあります。こんにゃくや海藻、きのこなどボリュームがあって低カロリーなので、満腹感が得られます。
肉類は脂を取り除く工夫をしましょう
肉は、脂身の少ない赤身がおすすめです。脂身が多いものは、調理前に取り除きましょう。煮たり、蒸したりすれば、余分な脂がさらにカットできます。
料理には植物性の油を使いましょう
飽和脂肪酸(牛脂)などは動脈硬化を促進します。不飽和脂肪酸を多く含む植物油を使用しましょう。フッ素加工のフライパンを利用すれば、油の量を減らせます。
食塩は減らしましょう
塩や醤油の代わりに、香辛料(こしょうなど)や出汁、レモンなどを使ってみましょう。
食べ方のポイント
良好な血糖コントロールを維持するためにも、食後に起こる急激な血糖値の上昇を避けなければなりません。毎日の食事の方法や食べる順番を少し変えるだけで、食後の血糖値の上昇を防ぐことができます。
よく噛んで、ゆっくりと食べましょう
急いで食べると、糖質が急激に吸収されて、血糖値が上がるので、ゆっくり食べましょう。よく噛むことで、早食いを防ぎ、満腹感も得られやすくなります。
食事のエネルギー量を均等にしましょう
適正なエネルギー量を守っても、1回の食事量が多かったり、少なかったりすると、血糖値が乱れやすくなります。エネルギーをバランスよく配分しましょう。
1日3食、規則正しく摂りましょう
食事を抜くと、まとめ食いにつながりやすく、遅い時間の食事や間食も、血糖値が上がりやすくなる原因となります。1日3食、決まった時間に食べるようにしましょう。
ベジファーストを心がけましょう
食事をするときは「野菜」から!
最も血糖値が上昇しやすいのは糖質を多く含む炭水化物です。食事をするときは炭水化物の摂りすぎを避け、はじめに野菜、次に主菜(肉・魚など)、最後に主食(ごはんやパンなど)を食べると、食後の血糖値の上昇が緩やかになるとされています。
摂津市公式キッチンでは…
摂津市保健センターで実施している糖尿病性腎症重症化予防事業の調理実習(摂津市栄養士会作成)を参考にレシピを掲載しています。

いかとオクラのピリ辛炒め

切干大根ときゅうりの梅酢和え

この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1386
ファックス:06-6383-5252
メールでのお問い合わせはこちら