校長室から
音読のすすめ
子どもたちの毎日の宿題に「音読」があります。ご家庭では、毎日音読を聞いてカードにチェックしていただき、いつもありがとうございます。ところで、なぜ、学校は毎日音読の宿題を出すのか。私自身も長い教員生活で当たり前に(漢字・計算・音読)の三点セットで宿題を出し続けてきましたが、その理由を深く考えたことはなかったように思います。
先日、人間の「生きる力」を育てる脳科学的な教育法の開発を目指して研究されている、東北大学助教で医学博士の榊浩平先生の講演を聞く機会がありました。榊先生によると、「考える、理解する、覚える」といった認知機能や「がまんする、人を思いやる、気持ちを伝える」といった非認知能力をつかさどる脳の前頭前野は「夢への扉を開ける脳」であり、10代で急激に発達するため、この時期にどれだけ育てるかがとても大事だということです。そして、前頭前野を育てるためには、とにかく使うことのみ。では、何をしている時に前頭前野が活発に使われているかというと、榊先生の研究の実証から、「簡単な計算をできるだけ速く正確に解いている時」と「本を音読している時」なのだそうです。残念ながら、ゲームやスマホをしている時は、空間認知や指を動かすための脳は動くけれども、前頭前野は全く使われていないのです。お話を聞き、自信をもって、授業や家庭学習に計算タイムや音読タイムを取り入れていきたいと思いました。
ちなみに…。脳は発達もするけれど衰えても行くもの。前頭前野の発達は30才がピークで、使わないと衰えるだけ…。いかに維持するかが大切になってきます。少しでも維持したいものです。そこで、ぜひ、お子さんと一緒に宿題の音読をしてみてはいかがでしょうか。計算ドリルをゲーム感覚で競争するのも良いかもしれません。大人も前頭前野を鍛えられるだけでなく、お子さんとの楽しいコミュニケーションの時間にもなるのではないでしょうか。忙しい毎日ですが、毎日の習慣に、音読を取り入れてみませんか。
令和8年2月
校長 猪本 澄子
力強く、前へ!
二学期末を迎え、令和7年(2025年)も残りわずかとなりました。保護者のみなさま、地域の方々には、様々な場面で本校の教育活動にお力添えをいただき本当にありがとうございました。
運動会を終え、11月、12月の各学年の取組みは非常に充実しており、例えば、2年生の「おもちゃランドへようこそ!」では、2年生が手作りのおもちゃやゲームを考えて制作し、招待した1年生を上級生らしく楽しませていました。4年生は「Dream マップ」の取組みで、「社会人トーク」として8社の企業の方にお越しいただき、働く大人との対話を通して自分の将来をより具体的に描いていきました。6年生は「平和学習報告集会」を開き、一学期から取り組んできた平和学習のまとめを、下級生に向けて言葉と合唱で発表したりプレゼンしたりしました。子どもたちは、しっかりと目的意識をもつことで主体的に活動し、異学年や異年齢の相手との交流を通して相手を意識して伝えたり受け止めたりすることを学び、また、自己有用感を得られる貴重な経験を得ました。子どもたちの姿に、巳年にふさわしく、脱皮する蛇が象徴する「成長」が感じられました。
令和8年(2026年)は、「前進」の象徴である午年の中でも特に、物事が発展し「ウマくいく」という縁起の良い「丙午(ひのえうま)」の年だそうです。新しい挑戦や飛躍に良い年で「力強い前進」の象徴。力強く地面を蹴って前へ前へと進む馬のように、新しい年が三宅柳田小学校の子どもたちにとって素晴らしい年になることを願っています。
三学期もよろしくお願いします。どうぞ良いお年をお迎えください。
令和7年末
校長 猪本 澄子
読書しませんか
夏に行われた第49回摂津市読書感想文コンクールに、今年もたくさんの児童が応募してくれました。そして、選考の結果、6名の児童が入選を果たしました。そのほかにも、様々なコンクール等で入賞のお知らせが続々と届いており、とても嬉しく思います。児童集会などで表彰させていただく予定です。
ところで、私が小中学生の頃は、夏休みには必ず読書感想文の宿題がありました。最終日まで苦戦して結局あらすじの要約に終始して原稿用紙を埋める…なんていう苦い思い出もあるくらい、最も苦手な宿題でした。感じたことを、自分の経験と結び付けて具体的に表現したり、読書の前と後での自分の考え方の変化や、本から学んだことをこれからの生き方にどのように生かしていきたいか、などを書くのがポイントのようです。
先日配布した、本校の「全国学力・学習状況調査結果より」のお便りの中で、質問調査結果から、読書の時間が少ないのでご家庭でも読書時間の確保などにご協力をお願いさせていただきました。調査は、平日1日当たりの読書時間をきくもので、「2時間以上」から始まり「1~2時間」「30分~1時間」「10分~30分」「10分~0」「全くしない」の6段階で回答します。「全くしない」と回答した割合が、本校は46%で、全国の29%に比べても非常に高い結果でした。子どもたちは、宿題や習い事ややりたいことで忙しく、読書する時間の確保がなかなか難しいのではないかと想像できます。私自身も、平日は家で読書する時間が「0」の日がたくさんあります。スマホは触るけれど…。でも、本を読むことは大好きです。読みたいなと思う本も次々と出てきて、購入したものの読めていない本もたくさんあります。
AIが読書感想文を書いてくれる時代ですが、心を動かされ、生き方に影響を与えられるような生きた経験は、実際に本を手に取り、自分で読んで感じなければ決して得られないものではないでしょうか。少し意識して、生活の中に読書の時間を増やしていきませんか。
令和7年12月
校長 猪本 澄子
「みんな大好き!やりきる!思いやりのある三宅柳田小学校」
「みんな大好き!やりきる!思いやりのある三宅柳田小学校」
今年度の児童会目標です。年度初めに、子どもたちが「自分たちの学校、こんな学校にしたい!」という思いをもって考えました。先週10月25日(土曜日)に開催した運動会も、このスローガンのもと取り組みました。子どもたちは、練習してきたことを120%出し切っていたと思います。一人ひとりが主役の表情で輝いていたのが印象的です。特に6年生のフラッグの団体演技は見事でした。練習では、「歩幅をそろえる」「息を合わせる」といった動作の一つ一つに互いを思いやる気持ちが必要で、なかなかうまくいきませんでした。自分たちの練習を録画して観たり話し合ったりしながら何度も何度も練習しつくり上げた演技は、当日、観ている人を感動させるほどに仕上がりました。演技している子どもたち自身が、心を一つにしてやりきる心地よさを体感したのではないでしょうか。
「子どもたちが主役の、子どもたちがつくる運動会」を目指してきましたが、子どもたちは、素敵な脇役にもなってくれました。前日準備、係の仕事、応援、そして転んだり落ち込んだりしている友だちへの思いやりの言葉、支えなど…目立たないけれど、実はとても大事で、そんな脇役の力がなければ決してつくり上げることはできなかったと思います。そして、さらにそんな子どもたちを練習期間から支え励ましてくださったご家族や地域の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。当日も、たくさんのご声援をいただきありがとうございました。
令和7年11月
校長 猪本 澄子
三宅柳田小から宇宙へ!
日本時間8月10日、大西卓哉宇宙飛行士が無事に地球に帰還されました。今年3月からの国際宇宙ステーション(ISS)での滞在期間中は、日本実験棟「きぼう」での様々な実験や生活の様子が、報道等でたくさん紹介されていました。
実は二年前、JAXAから学校に一本の電話が入り、大西卓哉さんがISSの長期滞在をされること、そして、大西さんが小学一年生の時、三宅小学校に半年間ではありますが在籍されていたこと、さらには、所縁のある機関の記念品を宇宙飛行に同行させていただけるという話をいただきました。にわかには信じがたい突然の連絡に大変驚きましたが、その後はわくわくした気持ちがどんどん膨らみ、大西卓哉さんや宇宙のことがぐっと近くに感じられるようになりました。
当時(令和5年度)の全校児童と教職員で作成したフラッグは、大西卓哉宇宙飛行士と一緒に宇宙を旅し、ISSから無事に持ち帰られ、現在は米国ヒューストンにてNASAが管理をしてくださっているそうです。最速で来年1月以降に、三宅柳田小学校に戻ってくるとのこと。
なんとも夢のある話ではないでしょうか。世界で、宇宙で活躍されている三宅柳田小学校の先輩の話を、未来ある子どもたちと共有していきたいと思います。子どもたちがそれぞれの未来で、自分らしく輝きながら活躍してくれることを願って…。
令和7年10月
校長 猪本 澄子
「夢」を「目標」にするには
「将来の夢や目標を持っていますか」
4月に実施された令和7年度全国学力・学習状況調査の質問事項の一つです。本校の6年生は、88.5%の児童が「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と肯定的に回答しました(全国では83.1%)。
「夢」と「目標」はひとくくりにして捉えられがちです。しかし、日本選手として初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさんは、その表彰式典のスピーチで、「(若い選手たちには)大きな夢を見てほしい。一方で、夢と目標の違いを知ってほしいのです。夢を目標にするには何が必要なのかを、真剣に考え抜いてください。」と語っておられました。夢は必ずしも現実的ではないけれど、目標は現実にすることができる。夢を見るのは楽しいが、目標は難しく、挑戦を伴う…。「夢」と「目標」の違いをはっきりと認識し、プロ野球選手になるという大きな「夢」を持ちながらも、それを現実にするためには毎日の練習と準備が大事だという信念を守りながら、自分の「目標」を定め続けたというイチローさんの言葉は、深く、重みを感じました。
さて、今日から二学期です。様々な大きな行事や体験的な学習等を通して、さらに学びを深めていきます。目の前の取組みをいかに自分事として捉え、難しく、挑戦を伴う「目標」を定めていくのか、子どもたちに問うていきたいと思います。また、夢や目標の質問に肯定的に答えられなかった児童も、将来を具体的に描き希望を持ち歩んでいけるよう、教職員みんなで支え、励まし続けていきます。
令和7年8・9月
校長 猪本 澄子
みやなサミット~もっと素敵な三柳小になるために~
6月19日、三宅柳田小学校で初めての「みやなサミット」が開催されました。山の頂上や最高点を意味する英語の「summit」。転じて、主要国のトップである首脳らが集まって開かれる会議を「サミット」と呼び、G7やG20が有名ですが、企業や業界のリーダーが集まる会議にも使われたりするそうです。なんだか凄いことができそうなこの響きに、参加する各委員会のリーダーたちは、誇りと責任、そして緊張感をもって臨んでくれました。
第一回みやなサミットは、「みんな大好き!やりきる!思いやりのある三宅柳田小学校」という児童会目標のもと、各児童委員会が、「学校がもっとステキになるために」やってみたい「企画」を持ち寄り発表し合いました。教員の出番はゼロの、子どもたちだけの会議です。
「自分たちの意見や行動で学校が良くなった!」という実感を児童会活動や学級活動を通して味わい、達成感や自己有用感を感じてほしいと、教職員みんなで意思統一してスタートした令和7年度。委員会活動において、「子どもたちが主役の、子どもたちがつくる三宅柳田小学校」の具体的な取組みの大きな一歩を踏み出しました。それぞれの企画を実現していくことは簡単ではないと思いますが、粘り強く取り組んでくれることを期待しています。取組みの様子は、学校HP「MY(みやな)Diary」でも紹介していきます。
令和7年7月
校長 猪本 澄子
唯一無二
史上最速で横綱に昇進した大の里関が、「横綱の地位を汚さぬよう稽古に精進し、唯一無二の横綱を目指します」と口上を述べられました。子どもの頃、相撲好きの母親がテレビの前に座り、横綱に昇進した力士がどんな四字熟語を使って口上を述べるのかを興味深そうに観ていた記憶が蘇ってきました。普段は大相撲を観ることもない私ですが、このニュースがなんだかとても心に留まったのは、そんな子どもの頃の経験が影響しているからかと思うと、何でもない毎日が積み重なって今の自分があるということを改めて実感しました。
さて、三宅柳田小の学校教育目標の一つめに、「やさしく思いやりのある子~自分も他人も大切にし、多様性を認められる子どもを育てる」を掲げています。今年度は、すべての学年で、自分や友だちの「もちあじ」を知り大切にする学習に取り組んでいます。「もちあじ」の学習をとおして、自分を見つめ自分を好きになったり(自己肯定)、相手の行動の奥にある思いに気づく(他者理解)気持ちを育てたいという願いがあります。この学習をしている時の子どもたちは、とても優しい顔をしています。あなたのもちあじはあなただけのもの、あなたは唯一無二のかけがえのない大切な存在と、お互いを大切にし合える時間だからです。そして、大切にし合える仲間とのつながりをとおして、一人では知ることも感じることもできなかった多様なものの見方や考え方を獲得し成長してほしいと願っています。
「唯一無二」という四字熟語を選んで決意を語った大の里関。自分のもちあじに誇りをもち、強さや技だけでなく人間性も含め、もちあじを磨き続ける覚悟を表明されたのではないでしょうか。
令和7年6月
校長 猪本 澄子
ひとは ひとをよろこばせることが 一番うれしい
新学期が始まり、約1か月がたちました。4月23日からは1年生の給食もスタートし、5時間授業に。小学校生活が本格的になり、少し疲れが出るころかもしれません。
4月30日には、全校児童が体育館に集合し、児童会委員が計画した「1年生を迎える会」を行いました。2~6年生が校歌を歌って1年生に聴いてもらったり、1年生も参加して○×ゲームをしたりしました。司会の児童会委員が、「1年生も安心して参加できるように」「1年生も楽しめるように」「1年生も一緒に歌えるようになるのが楽しみ」など、終始、1年生を喜ばせようと声をかけ、全校児童はそれに協力していた姿が印象的でした。また、きょうだい学年である6年生は、1年生の教室に行き給食当番や掃除の仕方を教えてくれたりもしています。1年生から笑顔で「ありがとう」と言ってもらえて、6年生も本当に嬉しそうです。
「人間が一番うれしいことはなんだろう?長い間、ぼくは考えてきた。そして結局、人が一番うれしいのは、人をよろこばせることだということがわかりました。実に単純なことです。『ひとはひとをよろこばせることが一番うれしい。』」
アンパンマンの作者 やなせたかしさんの言葉です。(朝ドラ「あんぱん」に影響されて読んでみた、やなせさんの著書「明日をひらく言葉」(PHP研究所)より。)小さなことでも、相手のことを想いながら自分にできることをすれば、相手はよろこんで笑ってくれます。その笑顔を見ると、自分も嬉しくなります。1年生に対するみんなのあたたかい言葉や行動が、それを物語っているように感じました。
令和7年5月
校長 猪本 澄子
学びたいことがある、会いたい仲間がいる 「たい!」のあふれる学校をめざして
やわらかな日差しが降り注ぐ春、75名の新入生を迎え、全校児童466名、教職員総50名で、三宅柳田小学校の令和7年度がスタートしました。
保護者の皆様、地域の皆様には、日頃より本校の教育活動をご支援いただき、心より感謝申し上げます。
さて、本校では、授業や生活の中で自分なりの「問い」を持ち解決することを通して、子どもたちの主体的な学びの実現に向け取り組んでいます。今年度は、児童会活動や学級活動においても、子どもたちが自分たちで考え行動することで「やってみて良かった」「自分たちの意見や行動で学校が良くなった」といった達成感や自己有用感を感じられるように、さらに取組みを深めていきます。
人は誰でも、幼いころはいろいろなことに興味を持ち「知りたい!」「やってみたい!」「できるようになりたい!」という意欲にあふれていたはずですが、いつの間にか「どうせできないし」「ムリ」といった諦めや無力感も学んでしまうものですよね。
三宅柳田小学校の子どもたちには、失敗もあるかもしれないけれど、できるだけたくさんの成功体験を積み重ねながら、粘り強さやたくましさも身に付けていってほしいなと思います。子どもたちの意欲を持続させ、高められるような教育活動に教職員全員で取り組んでまいります。子どもたちが主役の、子どもたちがつくる三宅柳田小学校。今年も楽しみです。
今年度も皆様方の温かい励ましと、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和7年4月
校長 猪本 澄子
凛と
「一月往ぬる 二月逃げる 三月去る」という慣用句がありますが、実際に、あわただしくあっという間に過ぎていくと感じられる方も多いのではないでしょうか。本校の1月2月は、3年生が「昔のくらし」の学習の「七輪体験」で地域の方にお手伝いいただいたり、4年生が「Dream map」の学習で近隣の企業の方から「仕事」について教えていただいたり、α共室の発表会が開催されたりと、地域の方から学ぶ機会をたくさんいただきました。子どもたちにとって「教わる」ことも貴重な体験ですが、活動を通して地域の大人と何気ない会話をしながら交流させていただいたことが、何より心温まる時間であり、「地域の中の自分」を実感できる時間だったのではないでしょうか。
さて、私は、「凛とした」という言葉が好きです。この言葉からは、凛々しさや清々しさ、芯の強さなどをイメージします。これまでやってきたことに自信と誇りを持ち、襟を正し胸を張って堂々としている姿が感じられます。3月を迎え、1~5年生は「進級」が、6年生はいよいよ「卒業」が迫ってきました。この一年間やこれまでの小学校生活を振り返ると、自分自身が驚くほど成長していることに気づくでしょう。もしも、頑張り切れずに悔むことがあったとしても、謙虚に内省して次につなげようとしているなら、堂々と胸を張ってほしいのです。そして、支えてくださった周りの人たちへの感謝も忘れずに。令和6年度の残りの時間はわずかとなりましたが、「あっという間に去ってしまった3月」とならないように、一日一日を大事に過ごしたいものです。そして、「凛とした」姿で、それぞれの次の一歩を踏み出してほしいと願っています。
一年間、本校の教育活動にご理解ご協力いただき、本当にありがとうございました。次年度もよろしくお願いいたします。
令和7年3月
校長 猪本 澄子
平和を願う
全校平和集会で6年生が平和学習の取組みを報告しました。6年生が、修学旅行で広島を訪れ実際に観て聴いて感じたことを自分の言葉で伝えている姿に、下学年の児童も真剣な表情で聞き入っていました。歌「いのちのリレー」も素晴らしく、心に響く歌声でした。
2歳で被爆し、12歳で原爆による白血病と診断された佐々木禎子さんは、8か月の入院生活の末亡くなったそうです。6年生は、禎子さんや戦争で奪われたたくさんの命のことを知り、今の平和がけっして当たり前ではないことを学び、広島の平和記念公園の原爆の子の像の前で「二度と戦争を繰り返さない」と誓い、折り鶴をささげました。そして、「生まれてきたこと、育ててもらえたこと、出会ったこと、笑ったこと、そのすべてに『ありがとう』、この命に『ありがとう』 」とメッセージを伝えてくれました。
今年、「核兵器のない世界を実現するために努力し、核兵器が二度と使われてはならないと証言を行ってきた」ことが評価され、日本被団協がノーベル平和賞を受賞されました。ノーベル賞の選考委員会は、「いつの日か、被爆者が存在しなくなるときが来るだろう。しかし、記憶をとどめる継続的な取組みによって、日本の新しい世代は被爆者たちの経験とメッセージを継承している。人類の平和な未来に不可欠な条件を維持することに貢献している。」と活動を受け継ぐ意義も強調されています。
12月8日は不戦の日です。今一度、平和を願い、私たちにできることについて考えたいと思いました。
令和6年12月
凡事徹底
先週、第17回運動会を無事に開催することができました。運動会という大きな行事に向けて、約一か月間、練習や準備を行ってきました。その過程で、児童は、「もっとうまく踊るためには?」「もっと速く走るためには?」など自分なりの問いの答えを探しながら努力したり、集団としての目標達成のために支え合い声を掛け合いながら絆を深めたり、大きく成長できました。運動会当日は、精一杯演技するキラキラの笑顔も、やり切って満足気な顔も、転んでも立ち上がり歯を食いしばって走り切る姿も、「がんばれー!」と声の限り応援する姿も…、みんなみんな輝いていて感動しました。
ご家庭では、楽しいことばかりではなく、練習のしんどさや疲れ、うまくいかない気持ちなども見せていたのではないでしょうか。子どもたちをいつも励まし支えてくださっているご家族のみなさまには、感謝の気持ちでいっぱいです。当日も、たくさんの方に観ていただきありがとうございました。
さて、大きな行事の後は特に踏ん張り時だと感じます。誰だって、やる気が起きなかったり余韻に浸っていたい気持ちになったりしますよね。だから、こんな時期こそ『凡事徹底』の素晴らしさを伝えたいと思います。最後までやり切る、掃除をする、「ありがとう」や「ごめんね」を伝える、時間を守る、人の話をしっかり聞く、規則正しい生活をするなど、当たり前のことを当たり前にするって、もしかしたら、目標に向かって努力することと同じくらい、いやもっと難しいことかもしれません。児童の、掃除時間に黙々と廊下を水拭きする姿、誰も見ていなくても落ちていたごみを拾ってくれる姿、授業準備を整えてチャイム着席している姿…、私には、どの姿も運動会に負けないくらい輝いて見えます。
当たり前のことを当たり前にできるって素晴らしい!
令和6年11月
支えが力になる
パリ2024オリンピック・パラリンピックが9月8日に閉幕しました。数々の名場面が生まれました。非常に個人的ではありますが…。私のベスト3は、1点が遠かった日本男子バレーボールのイタリアとの準々決勝の試合。3セットストレート勝利まで3点差をつけて迎えたマッチポイントでしたが、あと1点を取りきることができず逆転負けを喫しました。「油断」なのか「運」なのか…。そこには、決して「技の力」だけでは測れない何かがあるのだろうと、勝負の世界の難しさを感じました。ベスト2は、ビーチバレー女子決勝でネット越しに両チームが口論になったとき、会場に流れたジョン・レノンの「Imagine」を観客が大合唱し、口論していた選手たちが笑顔に変わったシーン。平和を願う気持ちの力や歌の力を感じずにはいられませんでした。そしてベスト1は、アスリートの方々の試合後のコメントです。オリンピックでもパラリンピックでも、勝っても負けても、共通して語られるのが「支えてくれた人たちへの感謝」と「次の目標」でした。一人で血のにじむような努力を重ねてきたであろうトップアスリートの方々ですが、たくさんの人に支えられてさらに強くなれるのだなと、そして、支えがあるからこそまた頑張ろうと思えるのだなと感じました。
改めて、ご家庭や地域の皆様の日頃からのご支援に感謝申し上げます。また、学校は、子どもたち同士が「支え合う場」でもあります。仲間と学ぶことで、考えが広がったり深まったり、一人ではたどり着けなかったところまで到達することができます。自分の発した言葉は、誰かの元気や勇気につながっているかもしれません。
さて、今日から運動会練習が始まりました。運動会が楽しみな人も苦手な人もいると思います。子どもたちには、一人ひとりのもちあじを大事にし、素敵なもちあじが発揮できるよう、お互いに関心を持ち支え合いながら今年の運動会をつくり上げてほしいと期待しています。
令和6年10月
「セレンディピティ」を引き寄せるために~ふとした偶然をきっかけに幸運をつかみとる~
「なぜ勉強するの?(しないといけないの?)」という質問を子どもから受けて答えに困ったことはないでしょうか。私自身も子どもの頃は、学べる環境があることに感謝する思いには至らず「させられている」と感じることもありました。歳を重ね、もっと真剣に勉強しておけばよかったと悔むことや、学び続けられる人でありたいという思いは増しているように感じる今、知らない言葉や自分にはなかった発想に出合うことはとても楽しいものです。
先日、ある講演で聞いた「なぜ勉強するのかというと、『セレンディピティ』を引き寄せるため。」という言葉が強く心に残りました。なるほどなぁと思いました。セレンディピティ(偶然を捉えて幸運をつかみ取ること)の代表的な例として、イギリスの科学者アイザック・ニュートンが、木からリンゴが落ちる様子を偶然目にしたことをきっかけに「万有引力の法則」をひらめいたという有名なエピソードがあります。当たり前ですが、ニュートンと一緒にリンゴが落ちる様子を見たとして、みんなが万有引力の法則を発見できるわけではありません。そこには、ニュートンが努力して培ってきた「偶然を捉える力」と「幸運に変える力」があったのだと思うのです。どう捉えるか、どう生かすかは本当に人それぞれ。
さて、今日から二学期です。日々の授業はもとより運動会、林間学校、修学旅行などの行事や校外学習、体験活動など、学ぶ機会が盛りだくさんです。三宅柳田小の子どもたちには、ぜひ、主体的に学んでほしいと思います。しっかりと学びに向き合い、そこから得た経験や知識はきっとセレンディピティを引き寄せる力につながっているのですから。
令和6年9月
時計の時間と心の時間
早いもので、一学期も残すところ3週間となりました。4月からの3か月間は、私にとっては「あっという間」でしたが、果たして、子どもたちにとっても「あっという間」だったのだろうか…?そんなことを考えていると、ちょうど6年生が国語科の説明文「時計の時間と心の時間」を学習していました。心理学者の一川誠さんが教科書のために書き下ろした教材です。一川さんによると、「時間」には「時計の時間」と「心の時間」という性質の違う二つの時間があり、「心の時間」は、心や体の状態、身の回りの環境などによって進み方が違ったり、人それぞれに違う「心の時間」の感覚を持っていたりするというのです。だからこそ、その性質を知ったうえで「時間」と付き合う知恵が、私たちには必要だと述べられています。
なるほど、確かに心当たりのある話です。目的地までの移動時間、行きは長く帰りは短く感じられたり、同じ10分間でも行列に並ぶのとゲームや読書に熱中するのとでは全く感じ方が違ったり。感じ方の違いといえば、時間に限ったことではありません。同じ出来事に遭遇しても、その時心に余裕があるかどうかで、ピンチと捉えるかチャンスと捉えるかは違ってきます。自分が感じている状況が、必ずしも事実(現実)とは限らないのです。だからこそ、多面的・多角的に物事を見たりゆったりとした心持ちで事にあたりたいなあと思うのです。
さて、夏休みまでの3週間、与えられた「時計の時間」はみんな同じです。どんな「心の時間」となるか、悔いのないように大事に過ごしたいものですね。
令和6年7月
子どもの安全を守る
外を歩いていると、あちらこちらのご家庭の庭先に、紫陽花の花が色づき始めているのを見かけるようになりました。「もう紫陽花の季節?」と思っていたら、やはり今年は例年よりも開花が随分と早いようです。例年より早く夏がやって来たような暑さの日があったり、梅雨の終わりのような大雨の日があったりして、季節外れの異常気象が「異常」ではなく当たり前になっているようにも感じます。学校では、熱中症や水の事故、遊具や施設の事故等が起こらないよう、子どもたちに注意喚起し全教職員で事故防止に努めています。
また、6月は大阪府「子どもの安全確保推進月間」です。大阪教育大学附属池田小学校での痛ましい事件のあった6月8日は「子どもの安全確保・安全管理の日」とされています。本校でも6月6日に防犯訓練を行う予定です。5月27日には、暴漢の侵入を想定した教職員の訓練を、摂津警察のご指導の下実施しました。子どもたちが安全安心に楽しく学校生活を送ることができるよう、点検・強化を図ります。保護者の皆様には先日の引き渡し訓練にもご協力いただきありがとうございました。引き続きご協力をよろしくお願いします。
令和6年6月
心をひらいて
新学期が始まり一か月がたちました。毎朝校門に立って子どもたちが登校してくるのを迎えていると、様々な変化を感じます。桜が散り、初夏の日差しに変わってきました。また、子どもたちのあいさつの様子も変わってきました。自分から元気にあいさつしてくれる人や目を見てにっこりあいさつしてくれる人が増えました。少し恥ずかしそうに会釈を返してくれるようになった人もいます。でもまだまだ表情を変えずに通り過ぎる人も…。心を開くまでの時間は人それぞれですね。いつでも安心して自分を表現してもらえるように、私は毎日、心を開いてあいさつをし続けようと思っています。
さて、4月23日から一年生の給食がスタートしました。どきどき、わくわくの給食ですが、当番の仕事を6年生が手伝いに来てくれています。手伝うにあたり、「一年生はどんなことに困るだろう?」「一年生にとってどのように手伝うのが良いだろう?」と考えたそうです。「一年生にとって」というのがミソですね。さすが6年生。思いやりを感じたエピソードでした。
令和6年5月
主役は子どもたち
満開の桜が美しく咲きほこる春、78名の新入生を迎え、全校児童462名、教職員総数49名で、三宅柳田小学校の令和6年度がスタートしました。
保護者の皆様、地域の皆様には、日頃より本校の教育活動をご支援いただき、心より感謝申し上げます。
さて、三宅柳田小学校の学校教育目標をご存じでしょうか。(昨年度の学校教育 保護者アンケートでは「はい」「どちらかといえばはい」は61.1%と低い結果でした…。)
1.やさしくおもいやりのある子
2.自らすすんで学習し、さいごまでやりとげる子
3.たくましい気力や体力のある子
1では「優しさ」「思いやり」、2では「主体性」「意欲」「粘り強さ」、3では「たくましさ」など、もっと広く捉えると「忍耐力」「社交性」「自尊心」といった力の育成を目指しています。これらの力はすべて『非認知能力』、つまり数値での測定が難しい能力です。そして、この『非認知能力』を育むことは、『認知能力【計算力や語学力といった学力テストなどで測れる能力】』の育成にも生かされるようになるそうです。
三宅柳田小学校の子どもたちの幸福や自己実現にむけ、子どもたちが主役となって主体的に活動できるような教育活動を工夫し、数値で測れる力も測れない力もしっかりと育んでいけるよう、教職員全員で取り組んでまいります。
「主役は子どもたち」を合言葉に、今年度も皆様方の温かい励ましと、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和6年4月
校長 猪本 澄子
みんなで繋(つな)ぐ
冬休み期間中に、東大阪市の花園ラグビー場で開催された第101回全国高校ラグビー大会で、惜しくも準優勝の 国学院大学栃木高等学校。今大会ベスト8に残った中で、唯一高校日本代表候補のいないチームであり、そのことから今年のチームは「雑草軍団」とも呼ばれていました。
そのチームを率いる吉岡肇監督は、以前ラグビーについて次のように述べていました。
「ラグビーは自分勝手じゃパスはつながりません。仲間の分までタックルしてやるという気持ちがないと勝てないし、いい選手になれない。一つのボールをみんなで繋ぐところがすばらしい。繋ぐためには、選手が大人になっていくしかないのです。パスというのは、ボールに夢を託すのですから。」
本年の三宅柳田小学校も、寅(トラ)年にあたり、子どもたちや教職員、それぞれの夢が託されたボールをみんなで繋ぎ、みごとにTRY(トライ)できるよう、一丸となった取り組みを進めます。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
令和4年1月11日
校長 谷田 学





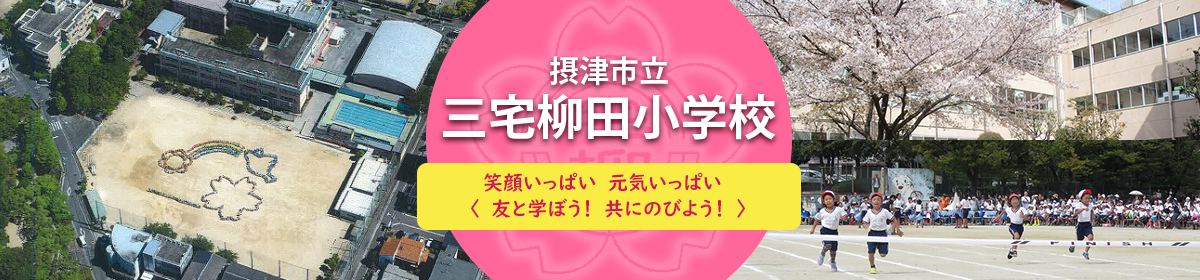

更新日:2026年01月30日